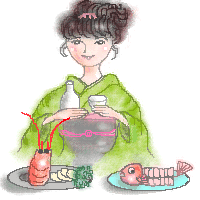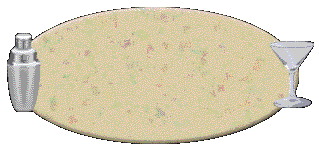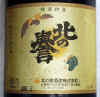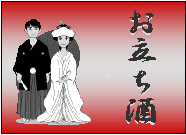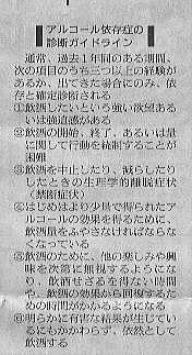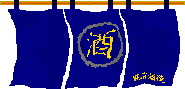だがそんなことは少しも自慢できることではない。酒の上での失敗は二日酔い程度で、自分ではまあまあの酒飲みだと自負?しているが、他の人から見ればどうなのかは分からない。
グデングデンに酔っ払ったり、人とケンカ口論したりするどといったことは全く記憶にない。私自身はワイワイ騒ぐのは好きだが、理性を忘れて酒の勢いでモノを言うのは大嫌いで、議論するのはいやだった。
よく「酒癖が悪い」といわれる人がおり、かつての勤務先でも何人かの人に手こずったことがある。不幸にもアル中になってしまった人も何人かいた。
よく「無くて七癖」などというが、飲むとその人の持っているいろいろな癖がモロに出てくるようだ。
酒飲みのクセを○○上戸などというが、タイプはいろいろあり、酔っ払ってくると大声になり笑う人、泣く人,怒る人、嘆く人、しつっこくなる人、説教魔、他人の悪口を並べ立てる人、等十人十色だが、押しなべて云えるのは、殆どが回りくどくなり、同じことを繰り返すのが特徴だ。またエッチな言動をとるようになるのも共通している。
私はどちらかといえば、いつもより冗長になり、快活にはなるが、平然とした顔して飲むほうだったので「強い」とおだてられた。余り酒席で「乱れた」ことはなかったと思う。
現役時代はいつも緊張して飲むほうだったので、皆と別れてから後でどっと酔いが回ってくるのだった。
家に到着した途端にバタンキューだったので奥方からよく「あなたはサケに飲まれるからダメ!」…とお叱りを受けた。翌日は二日酔いで頭がズキンズキン…こんなことを繰り返していた。
二日酔いにきくクスリはあるのだろうか
ネットに載っていたものを拝借させていただくと
(果物・野菜等系)サトウキビ キンカン レンコン いちじく ザクロ 柿 とうもろこし 白菜 ハチミツ 梅干し ごま (魚貝系)しじみ フグ
(ハーブ系)セイジ フェンネル ラベンダー ペパーミント ローズマリー ジュニパー カモマイル
(茶系)緑茶 コーヒー プーアール茶 ゴーヤー茶
(漢方系) ハンノキ カンゾウ ササ ウコン 葛根
(薬系)クマノイ キトサン ブドウ糖等など
さらに、レッド・アイ(ビール、トマトジュース半々のカクテル)などというものもあるようだ。
食べ方としては、そのまま、粥、茶、点滴、煎じる、ミックスする等などだそうだ。
だが私の体験ではすぐ効くものはない。水分を取り、ただひたすら時間の経過を待つのみだ。コーヒーのような利尿剤は効くかもしれない。若いときは半日程度で回復することが多かったが中年以降はだんだん時間がかかるようになってきた。もっとも最近は二日酔いとは縁遠くなった。仲間と飲む機会が少なくなったのだ。
一番いけないのはいわゆる「迎え酒」と称する方法で、二日酔いなのに、また酒を飲み、酔っ払って抑えようとするのは最悪だと思う。肝臓を痛めつけることは勿論、繰り返すと「アル中」になること間違いなしだ。 |
学生時代やサラリーマン初期の頃に流行っていたのは「トリスバー」というスタンドバーだった。
呑むサケは殆どハイボールと称するトリスウイスキーを炭酸で割った飲み物だった。ビールや日本酒は高かったし日本酒の2級や合成酒は、まずくて飲む気がしなかった。当時の日本酒は醸造方法が未熟であったため雑菌が入りやすく、サルチル酸のような防腐剤が混入されていたと記憶している。
|
 |
当時の安ウイスキーはモルトではなく、合成酒にカルメラで色をつけウイスキー風のニオイをつけただけの代物だった。サントリーの「白」とか「角」という本格ウイスキーは高価だったので余り飲めなかった。
しばらくたって「レッド」という商品が売り出され、味も少しウイスキーらしくなってきた。この合成酒もずいぶん飲んだ。美味いとか不味いとか云うより酔っ払うのが目的のような飲み方だった。
◆
北海道の酒は格別
30過ぎに転勤し札幌で4年間を過ごした。男女ともに解放的でよく酒を飲む土地柄だった。
ここの気候風土も影響があったのかもしれない。とにかくビールがうまかった。特に北八条通にあったサッポロビール工場直営のビアホールの生は絶品だった。他のコンテンツ「思い出話」でも少し触れたが、当時1000円出すと「呑み放題とジンギスカンの食べ放題」のコースがあった。ここは白樺の木々に囲まれたレンガ造りの建物でまるで外国にいるような雰囲気だった。
仲間には「豪のもの」がいて、大ジョッキ数杯をあけジンギスカン2〜3人前をぺろりと平らげるご仁もいた。
ウイスキーは余市にニッカの工場があり、殆どニッカを飲んでいた。
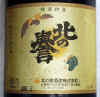
札幌の酒 |

ジンギスカン鍋 |

飲兵衛そろい踏み |

毛蟹 |

鰊漬 |
酒は「北の誉」と「千年鶴」というという銘柄をよく飲んでいたがいずれもなかなか美味い日本酒だった。
酒の肴は当然蟹や鮭、シシャモ、たらこ、ほっきやホタテ貝、など豊富な魚介類だが、冬には石狩鍋や鰊漬という独特の漬物を肴にしてよく飲んだ。酒の味を一段と引き立ててくれる食べ物が多かった。また自宅では生のイクラを買い求め醤油漬にして食べたがこれは絶品だった。
仕事が終わると、夜の歓楽街、薄野にもよく出かけたが、ハシゴ酒のあとは必ずといっていいほど仕上げにサッポロラーメンを食べていた。凍てつくような真冬の夜、飲み仲間と熱いラーメンをすするのはこたえられなかった。この北海道時代に本格的な酒飲みに成長?したのだった。
◆帰ってきたヨッパライと歌
酒に関連がある歌は古今東西を問わず数え切れないほどある。「酒」といえば酔うと歌いたくなるのはどこでも同じだろう。
かっこいいのは「乾杯の歌」だ。ヴェルディのオペラ「椿姫」の第一幕で歌われる主役の二重唱と合唱だが、まず知らない人はいないだろう。杯を高く掲げて景気よく歌う。
メロディも美しく何度聴いても気分がよくなる。
| アルフレード: |
♪楽しい杯で喜びの酒を飲みほそう
はかないときを快楽にゆだねよう
愛を呼び覚ますときめきのうちに杯を飲みほそう
彼女のまなざしこそ、僕にはすべてに勝るのだから 乾杯しよう。 愛によって、熱い杯の間に口づけを得るだろう♪ |
| ヴィオレッタ: |
♪皆さんと一緒に楽しいときを過ごしましょう
喜びでないものは、すべてむなしいものです
楽しみましょう、はかない愛の花を
今楽しまなくては、すぐしぼんでしまいますわ
さあ、楽しみましょう
杯と歌が、夜々この楽園を新しくするのです♪ |
|
 |
クラシックの世界ではマーラーの「大地の歌」」は酒をテーマにし、聴いていると酔った気分のように陶然となるすばらしい名曲だ。中国の詩人であり酒仙の誉れ高い李白の詩が取り入れられたシンフォニーで歌曲が主体だ。当時中国の酒飲みは壮大にサケを飲んだらしい。朝から斗酒もへ一チャラだったらしい。
第1楽章 大地の悲しみに寄せる酒の歌( Das Trinklied vom Jammer der Erde)
・・・・詩仙・李白の詩→ 「大地は永遠だが、人生は短い。金色に輝く酒を今こそ飲み干そう。生は暗く、死も暗い。」
第5楽章 春に酔える者( Der Trunkene im Fruhling)
・・・・李白の詩→ 「人生が幻にすぎないなら、努力も苦労も何の甲斐もない。それより終日酒に溺れよう。」
|
またモーツアルトのオペラドンジョヴァニにも出てくるが、バッカスやヨッパライはオペラやオペレッタの登場人物としては欠かせない存在だ。。さらにシュトラウス一族のワルツやポルカには愉快な音が沢山出てくる。
「酒・女・歌」といウインナワルツはあまりにも有名だ。
 |
わが国にも沢山あるが「おめでたい」方の代表格は「黒田節」だろう。正調で歌われると勇壮で美しい民謡だ。
お座敷歌にも多数あるが「お立ち酒」などは非常に優れた歌だと思う。
ただ最近は婚礼の席でもあまり歌われなくなったようだ。 |
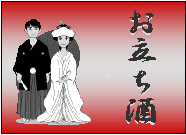 |
酔っ払ってカラオケで歌うとしたらどんな歌が多いのだろうか。
私自身はカラオケでも湿っぽい歌は難しいので歌えなかったが♪酒は涙かため息か、心の憂さの捨てどころ♪…という古い歌謡曲は知っていた。その昔フォーク・クルセダースが歌っていた「帰ってきたヨッパライ」という歌が好きでよく歌っていた。♪おらは死んじまっただぁ…天国よいとこ一度はおいで〜酒はうまいし、姉ちゃんはキレイだ ワッワー ♪ 等という調子よく愉快なウタだった。
また、美空ひばりの歌う酒の歌は絶品だといつも感じていた。
「のん兵衛」の歌う歌についてあるサイトで調べてみた。「飲兵衛でーた!」というサイトがあり、以下その一部を引用させていただいた。
アンケートに答えた結果を上位から10位まで転載させていただいたものだが、私が知っているのは4、6、7、10の4曲だ。アンケートの中で「ない、わからん、思いつかない」などと答えているケースが結構多いのは面白い。飲むときは歌どころではなく一心不乱に真剣勝負で飲むということなのかしら…
私の趣味からすると美空ひばりの「悲しい酒」が絶品だと思うのだが… これは余談だが美空ひばりはまさに不世出の天才歌手だと思う。以前オペラのアリアをお遊びで歌ったのを聴いたことがあるが、ヘタな本職顔負けのうまさだった。
このサイトは「のん兵衛」に関するいろいろなデータが載っていて面白い。
★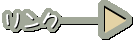 飲兵衛でーた
飲兵衛でーた
|
お酒にちなんだあなたの一曲は?
|
|
順位
|
得票数
|
回答
|
|
1
|
31
|
酒と泪と男と女
|
|
2
|
23
|
ない。
|
|
3
|
11
|
わからん。
|
|
4
|
9
|
「酒よ」吉幾三
|
|
5
|
7
|
日本全国酒飲み音頭(バラクーダ)
|
|
6
|
6
|
氷雨
|
|
7
|
6
|
北酒場
|
|
8
|
5
|
思いつかない
|
|
8
|
5
|
八代亜紀、『舟唄』
|
|
10
|
4
|
「悲しい酒」美空ひばり
|
|
◆
飲むと頭が冴えて閃くか?
否!ありえないことだ。飲み続けると脳細胞が破壊されてバカになるだけだ…と思いつつ今日もまた飲んでしまう。
全く意志薄弱だがこれが飲兵衛の飲兵衛たるゆえんである。
飲んでいて陶然となると頭の回転が速くなり?しゃべりまくる。大言壮語しハイになり、いいアイデアが次から次に浮かび、未来が突然開けるようないい気分になったことありませんか?
べらんめー、矢でも鉄砲でも持ってこい!コワイ物なんかねぇぞ!…てなもんだょな。
だが酔いがさめて冷静になるとろくでもない発想ばかりで、財布が超軽くなってションボリするのがおちだ。
だが「分かっちゃいるけど止められねぇ」のがサケだ。これの繰り返しが依存症につながると思うのだが…
◆
アルコール依存症
この世の中カラダにいいことだけしていても死ぬときは死ぬよ。タバコもコーヒーも甘いものダメとなると…
「生きていても仕方がねぇな」という気分になる。
だが真昼間から酒びたりになっているのは「アル中」である。
これは完全な中毒症状だから入院治療を要する。自分の身を滅ぼし家族を地獄に陥れる不幸な病気だ。
しかし、問題なのはその予備軍だといわれ最近問題になっている依存症だ。
飲酒をやめたくてもやめられない人が推計で国内に82万人もいるという。これは厚生労働省の研究班が全国調査をして割り出した数だ。それによると依存症の割合は男が1.9%女0.1%で平均すると1%程度だという。世代別には70歳台がトップで約3%を占めているという。
特に最近は女性のアルコール愛好者が増加しているのだそうだ。適量なら大いに結構なことだが、社会進出が急増する一方、子育てや家庭のイザコザなどでキッチンドリンカーといわれるタイプの依存症が問題になっている。女性の場合は男と異なり、特に肝臓への悪影響が大きいとも云われている。いずれにせよ本人の意思と、家庭・社会の理解がどうしても必要になると思われる。
酒飲みよ、心せよ!
暴言・暴力、飲酒の強要、セクハラ、等などアルコールによる問題行動の被害実態は調査によるとその被害者はナント3040万人と推計。
職場の人との飲酒が原因で困った経験のある人は10%おり、うち「からまれた」が50%「飲酒の強要が36%あった。
「被害を受けたことで人生や考え方に影響を受けた」と答えた人も被害者の13%にのぼった。
久里浜にある有名な治療専門病院である「久里浜アルコール症センター」の推計では依存症、430万人という説もある。
厚生労働省研究チームでは
「国民は飲酒の功罪の罪をもっと知る必要がある」としている。
これは酒飲みの私自身が反省もこめて十二分に認識すべき問題点だと思った。 |
|
|
|
 |
モノの本によると「日本酒で毎日1〜2合の飲酒はまあまあ、3〜4合の「飲み助」は10年以上経つと内科医や神経科医のご厄介になり、それ以上の「大酒のみ」は早ければ1年以内に、多くは数年後に、お医者さんのご厄介になる可能性が大である」ということだ。
酒飲みは大いに心したほうがよいでしょう。
飲みすぎは二日酔いに苦しむし、脳みそを破壊し、心臓の筋肉をもろくしてしまうので、よい事は何一つない。(これは私自身への警告なのだ!!) |
糖尿系の酒飲みにはよく「日本酒がダメならビールやワイン、ウイスキーならOK」などとうそぶいて飲んでいる御仁がいらっしゃるが、こんなこじつけのエクスキューズまでして飲みたいものなのか。
ま、気持は分からないでもないが…
締めくくりに酒飲みに耳寄りな話を紹介しよう
私自身が好きだからいうのではないが、日本酒を愛飲する人は知能指数が高くボケにくい?とのこと。
これはSという雑誌に載っていた記事だが、ある国立の医療研究センターの疫学の先生の調査結果として「日本酒とワインについて男女ともに一日に適量飲む人ほど知能指数が高くなる傾向があり、その他の酒類では飲酒と知能指数との関連は見られない」というものだ。
この説にはきちんとした根拠があるのだ。すなわち「日本酒やワインは醸造酒であり、その製造過程でさまざまな成分が生まれるからだ。赤ワインにはポリフェノールという酸化を抑える働きを持つ物質が豊富に含まれており、日本酒にもフェルラ酸という抗酸化物質が含まれている。いずれも病気や老化を引き起こす活性酸素をおさえ、動脈硬化や脳の老化を防ぐ働きがある。また日本酒によくマッチする和食も効果的だ。適度のアルコールは血管を広げて血液の循環を高めるといわれており、善玉コレステロールを増やして精神的なストレス解消にも役立つ。昔から「百薬の長」といわれている酒をうまく利用しよう云々…」
お断りしておくが、この効果はあくまでも適正酒量の範囲であり、飲みすぎは百害あって一利なしということだ。このことは本にも明記してあった。(04/11/30)もどる |