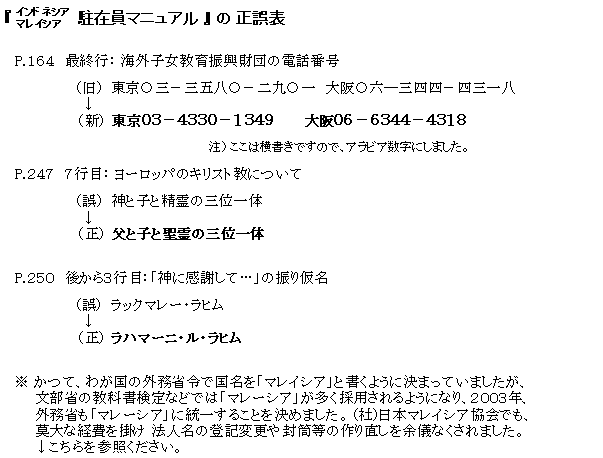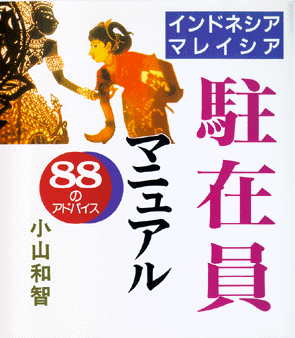
これぞ生きた異文化理解
社団法人 日本マレイシア協会
会長 塩川 正十郎
近年、マレイシアをはじめとする東南アジア諸国へ日本企業の進出が急ピッチで進み、大勢の日本人が同地で生活をするようになりました。
それに伴い、日常や職場において、現地の人々との様々なトラブルに直面することが多くなってきております。
それは、多様な人種・宗教・文化が混在する東南アジアにおける、異文化理解の欠如によるところが大きいと考えられます。
そんな中、本書では、これまでに起こった具体的なトラブルの事例を取り上げ、その予防と処理を通じて、東南アジアの人々と共に生きる知恵を紹介しており、駐在員の方や現地担当の方などに有用な情報を提供しています。
企業人だけでなく、これから社会人になる学生の方にも、ぜひ一読をお薦め致します。